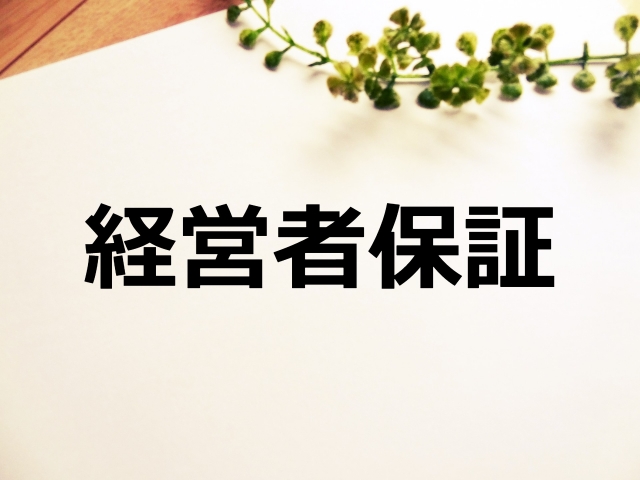
中小企業が金融機関から融資を受ける際、「経営者保証」が求められるのが一般的でした。
これは、企業が返済できなくなった場合に経営者個人がその返済責任を負う制度で、経営者にとって大きな精神的・財務的負担となってきました。
しかし2024年3月から、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度の申し込み受付が開始されました。
この制度を活用することで、経営者保証を避けつつ融資を受けることが可能となり、事業の成長や承継をスムーズに進めやすくなります。
経営者保証とは?なぜ問題視されてきたのか
経営者保証は、融資を受けた企業が返済できない場合に、経営者が個人資産を使って返済するという保証です。
この仕組みには以下のようなデメリットがあります:
- 経営者個人の財産リスクが大きい
- 新規事業への投資意欲が削がれる
- 後継者が保証を敬遠し、事業承継が進みにくい
こうした背景を受けて、政府は2014年に「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、保証に依存しない融資の促進を始めました。しかし、それでもなお多くの融資では経営者保証が付いているのが実情です。
【図解】従来と新制度の違い
[従来の融資] → 経営者保証が必要
[新しい保証制度] → 保証料を上乗せで経営者保証なし
2024年から導入された新制度とは?
経営者保証を外して融資を受けられる信用保証制度が、以下の3つです。
1. 事業者選択型経営者保証非提供制度
保証料を一定上乗せすることで、経営者保証なしの信用保証付き融資を受けられる制度です。
中小企業が自己判断で選択できる点が特徴です。
利用要件(一部抜粋)
- 過去2年分の決算書を提出済み
- 経営者に過度な役員報酬や貸付がない
- 債務超過または2期連続赤字でない
- 保証料の上乗せを了承していること
保証料の上乗せ幅(追加)
| 財務状況の評価基準 | 上乗せ料率 |
|---|---|
| 一定基準を満たす | +0.25% |
| 一部基準に満たない | +0.45% |
2. 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
上記制度の普及を促すための**期間限定の優遇制度(2027年3月末まで)**です。
主な特徴
- 保証料の上乗せ幅は上記と同じ(0.25%または0.45%)
- 国の補助により一部負担が軽減される(最大0.15%相当)
3. プロパー融資借換特別保証制度
これは、**既存の経営者保証付きプロパー融資(保証協会の保証なし融資)**を、
保証協会付きの保証なし融資に借り換えることができる制度です。
利用要件
- 対象企業が資産超過であること
- 財務健全性(EBITDA倍率など)を満たしていること
- 法人と個人資産の分離がされていること
こちらも2027年3月末までの時限措置です。
経営者保証をつけることのリスク
経営者保証には以下のようなリスクがあります。
| リスク内容 | 詳細 |
|---|---|
| 個人資産の責任負担 | 返済不能時、経営者の私有財産が差し押さえられるリスク |
| 意欲の萎縮 | 経営者が過度に慎重になり、成長投資を避ける可能性 |
| 事業承継の妨げ | 後継者が個人保証を嫌い、承継を断るケースも多い |
経営者保証なし融資を活用するメリット
✅ 経営者リスクの軽減
→ 万一の場合でも個人資産を守れる
✅ 事業承継の促進
→ 後継者が承継しやすくなり、スムーズなバトンタッチが可能に
✅ 意欲的な経営判断が可能に
→ 設備投資や新規事業にチャレンジしやすくなる
まとめ:制度の活用で企業経営をより自由に
経営者保証を不要とする新たな信用保証制度の登場は、中小企業にとって大きな転機となります。
保証料の上乗せというコストはあるものの、それ以上に得られるメリットは大きく、特に以下のような企業にとって有効です:
- 後継者への事業承継を考えている
- 成長投資を積極的に行いたい
- 経営者個人のリスクを抑えたい
制度の利用には、信用保証協会や取引金融機関との相談が必要です。早めに情報を収集し、自社に適した制度の活用を検討してみてください。


