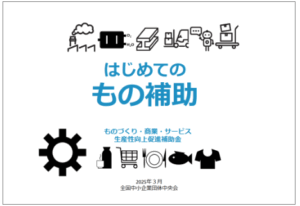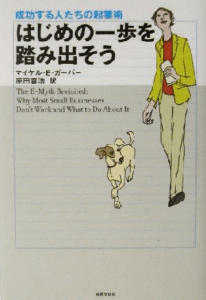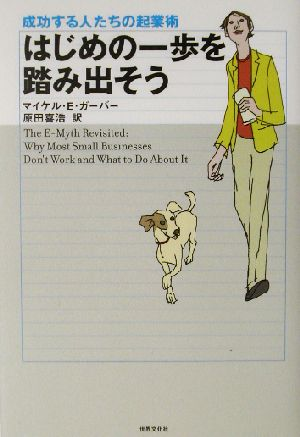
~事業発展プログラムと経営者の「志」~
本シリーズも第5回を迎えました。前回は、成功へのカギとして「仕組み化」「再現性」「起業家の視点」の重要性を取り上げました。今回は、いよいよ事業を発展させるための実践プログラムに踏み込んでいきます。
事業発展プログラムとは?
ガーバー氏は、優良企業をつくるためには偶然ではなく、意図的なステップが必要であると説いています。
そのために用意されたのが、次の2つの要素です:
- 3つのルール:思考と行動の前提
- 7つのステップ:実行のフレームワーク
📌【図解】事業発展プログラムの構造
┌──────────────┐
│ 3つのルール │
│・イノベーション │
│・数値化 │
│・マニュアル化 │
└──────────────┘
↓
┌──────────────┐
│ 7つのステップ │
│①人生目標の明確化 │
│②戦略的目標設定 │
│…以下続く │
└──────────────┘
それでは、前半の「3つのルール」と「ステップ①・②」を中心にご紹介します。
【ルール①】イノベーション:常に最善を求める姿勢
「イノベーションとは、最善の方法を探し続けること」
ここでいう“イノベーション”とは、画期的な技術や商品開発ではありません。むしろ日常の業務の中で「もっと良くできないか?」を問い続ける姿勢、つまり**日本流の「改善」**に近い考え方です。
【ルール②】数値化:改善は測定から始まる
イノベーションの効果を見極めるためには、「数値化」が欠かせません。数値をもとに現状を把握し、改善の効果を確認することで、組織として学習し成長できます。
📈【例:戦略的指標の一例】
| 指標名 | 内容例 |
|---|---|
| 経常利益率 | 利益性の基礎指標 |
| 顧客満足度 | サービス品質を図る |
| 経営自立度 | 個人依存を脱した運営体制の達成度 |
【ルール③】マニュアル化:一貫性の源
マニュアルと聞くと「融通が利かない」とネガティブな印象を持つ方もいますが、ここでの意味は異なります。
「オーケストレーション(自動化された調和)」
= 業務の標準化・明文化・一貫化
つまり、イノベーションと数値化を経た**“最善のやり方”を仕組み化する**ということです。これにより、属人性を排し、誰がやっても同じ品質が担保されるようになります。
ルールを回す「成長のサイクル」
🌀【図解:自己成長×事業成長サイクル】
- 数値化:現状を測定する
- イノベーション:改善策を試す
- マニュアル化:成果を仕組みに定着させる
→ さらに次の成長へ…
このサイクルを組織全体でまわすことで、会社も人も進化し続けることができます。
ステップ①:あなたが望む人生の目標とは?
ガーバー氏はこう述べています。
「事業とは、人生の目的を実現するための手段である」
つまり、事業計画を立てる前にまず、自分自身の**人生の目標(志)**を明確にすることが不可欠です。
この志とは、「売上〇億円」や「会社を上場させたい」といった“Do”や“Have”の目標だけではなく、「どんな生き方をしたいか」という**“Being”の目標**のことです。
志を明確にすると判断が変わる
「志に照らすことで、日々の行動が正しいかどうかを判断できるようになる」
例えば、今日の自分の言動が「志に沿った行動だったか?」と内省する習慣は、経営判断にブレを生じさせない土台になります。
ステップ②:戦略的目標の設定
戦略的目標とは、「将来、自社がどのような姿になっていたいか」という明確なビジョンです。
たとえば、ガーバー氏の書籍では、主人公のサラが経営する「オールアバウト・パイ」の7年後の姿を、鮮明に言葉で描写しています。
🎯【戦略的目標を設定するための問い】
- あなたの会社は7年後、何を提供しているか?
- どのような顧客に、どんな価値を届けているか?
- どのような組織構成で運営されているか?
志と目標がズレていないか?
戦略的目標を立てるうえで注意すべきは、前項で明確にした**“志”との整合性**です。
例:
- 志:「世界中に健康を届けたい」
→ 目標がニッチな国内事業に偏っていれば要見直し
ガーバー氏は、「偉大なビジネスの多くは、ごく普通の商品・サービスを扱っているが、やり方が違う」と言います。
つまり、「何を売るか」ではなく「どう売るか」が差を生むということです。
まとめ:会社経営の出発点は「経営者自身」
今回の内容を振り返ると、事業を発展させるには次の流れが重要です。
- 人生の目的(志)を明確にする
- 志と整合した戦略的目標を設定する
- イノベーション・数値化・マニュアル化を繰り返す