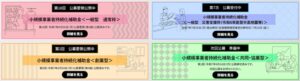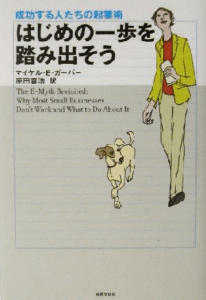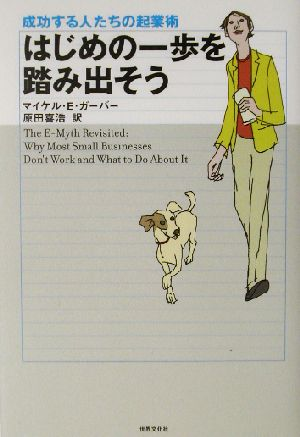
〜経営に失敗する本当の理由と3つの人格〜
前回の記事では、マイケル・E・ガーバー氏による名著『はじめの一歩を踏み出そう』の「まえがき」「はじめに」を解説しました。今回は、書籍の構成の中でも最初の重要なパート、「失敗の原因を知る」について解説します。
本書の全体構成
『はじめの一歩を踏み出そう』は、以下の3部構成です。
- パート①:失敗の原因を知る
- パート②:成功へのカギ
- パート③:成功するための7つのステップ
今回は、最も多くの経営者がつまずく「パート①:失敗の原因を知る」の前半に焦点を当てていきます。
起業家の「致命的な仮定」とは?
「事業の専門スキルがあれば、経営もできる」と信じて起業した人が大半であり、それが多くの事業が失敗する原因である。
これはガーバー氏が語る「起業家の神話」です。多くの経営者は自分の専門スキル、いわゆる「手に職」をベースに独立します。最初はそのスキルで売上が上がるかもしれませんが、やがて人材や資金など、専門外の課題に直面し、次第に経営の混乱に陥ります。
この混乱により、起業当初に持っていた情熱が薄れ、事業は停滞。最悪の場合、経営者が自分の事業に苦しめられてしまいます。
経営者に宿る「3つの人格」
事業を成長させるために欠かせないのが、経営者が持つ3つの人格のバランスです。
📌【図解:経営者の3つの人格】
| 人格 | 特徴 | 時間軸 |
|---|---|---|
| 起業家 | ビジョンを描く。理想主義者で未来志向 | 未来 |
| マネージャー | 組織を整える。現実主義者で安定を好む | 過去 |
| 職人 | 現場を支える。自ら手を動かす職人気質 | 現在 |
多くの起業家は以下のような比率で働いているといわれます。
職人:70%/マネージャー:20%/起業家:10%
これでは目先の業務に追われ、会社を“仕組み”で回すことができません。成長する経営者はこのバランスを意識的に整え、「職人」から「起業家・マネージャー」へシフトしていく必要があります。
成長ステージ別に見る経営の課題
会社には3つの成長ステージがあります。それぞれの段階で、主役となる人格も変化していきます。
🧩【図解:事業の成長ステージと人格の主役】
| ステージ | 主な特徴 | 主役となる人格 |
|---|---|---|
| 幼年期 | 社長=現場。全て自分で対応 | 職人 |
| 青年期 | 人を雇い始めるが混乱も多発 | マネージャー・起業家が必要 |
| 成熟期 | 仕組みが整い、持続的成長へ | 起業家・マネージャー |
幼年期:職人主導で突っ走る
この段階では、経営者が業務の全てを自分でこなします。顧客も増え、収益も上がりますが、時間的・体力的な限界がすぐに訪れます。
ここでの選択肢は2つ。
- 自分が動き続ける経営スタイルを続ける
- 自分の業務を他人でもできるように“仕組み化”する
後者を選ぶには、起業した目的を再確認しなければなりません。
「自由な時間と収入がほしい」という目的だけでは、組織化には限界があります。
青年期:人を雇って生まれる混乱
人手が必要になり、スタッフを雇い始めると会社は青年期に突入します。しかし、ここでよくあるのが「管理の放棄」です。
任せたはずの業務でトラブルが起き、再び社長が現場に戻る——この悪循環に多くの中小企業が陥っています。
「社長が働けば働くほど、社員が働かなくなる」
この状況を脱するには、社長が「職人」から「マネージャー・起業家」へと自らの役割をシフトさせる必要があります。
青年期の3つの選択肢
ガーバー氏は、青年期で混乱した企業が取りうる選択肢として次の3つを挙げています。
- 幼年期に戻る:業務を縮小して再び自分でこなす
- 倒産する:無理な拡大が招く結果
- 青年期を乗り越える:課題と向き合い、仕組みで事業を成長させる
この中で最も挑戦的なのが3つ目の「乗り越える」ことです。
これは、自社を“自分とは別の生命体”として捉え直し、志やビジョンを組織全体に注入するステージです。
成長の壁は「変化の壁」
ここで立ちはだかるのが、いわゆる「仕組み化の壁」です。
経営者がこれまでの自分を手放し、経営という旅の“次のステージ”に進む覚悟が求められます。
💬「なれるかもしれない自分になるために、いまの自分をあきらめよ」
― ナフマン・ブラツラフ(ユダヤ教の思想家)
まとめ:自分の今と向き合うことからすべてが始まる
今回は、『はじめの一歩を踏み出そう』の「失敗の原因」に関する部分を中心にご紹介しました。
- 自分はどの人格が強いか?
- 自社はどの成長ステージにあるか?
- どのような変化を受け入れる必要があるか?
こうした問いを持つことが、経営を次のステージへ導く第一歩となります。
次回は、「成功へのカギ」や、経営者に欠かせない「起業家視点」について解説します。どうぞお楽しみに。