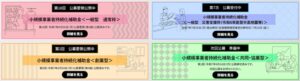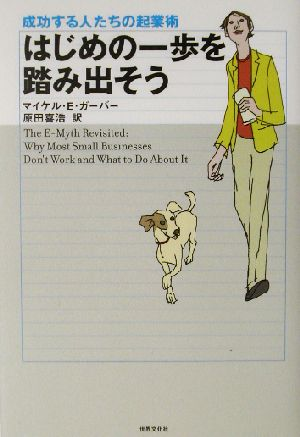
〜「仕組み経営」の原点を読み解く〜
書籍紹介と本シリーズの目的
世界中の経営者に影響を与えた名著『はじめの一歩を踏み出そう(原題:The E-Myth Revisited)』の内容を、ビジネスパーソン向けにわかりやすく解説していきます。
著者は「仕組み経営」の提唱者、マイケル・E・ガーバー氏。
本書は1986年に初版が発行され、改訂版は1995年、日本語版は2003年に登場。全世界で700万部以上、日本でも13万部以上のロングセラーとなっています。
📊【図解:本書の発行実績と評価】
指標 数値 世界販売部数 約700万部 日本販売部数 約13万部 初版発行年 1986年(米国) INC誌ランキング ビジネス書No.1
この本は「起業前の人向け」と思われがちですが、実際には10年以上経営を続けている社長からの共感も非常に多く寄せられています。
なぜ多くの企業が失敗するのか?
本書では、毎年多くの人が会社を立ち上げる一方で、以下のような厳しい現実を指摘しています。
- 起業1年目で40%が廃業
- 5年以内に80%以上が市場から姿を消す
その背景には、「専門スキルがあれば経営もできるだろう」という“致命的な仮定”があると指摘されます。
成功する経営の条件とは?
「経営者は“仕組み”をつくるべき存在である」
経営者が現場の実務に追われるのではなく、「自分がいなくても回る仕組み」を構築することが、事業の継続・発展には欠かせません。
多くの成功事例を生んだ書籍
『はじめの一歩を踏み出そう』を実践した企業には、次のような実績があります。
- ゴミ収集事業を年商400億円企業に(O2E Brands)
- 2人の社員から30万人規模に成長(BNI社)
- 年商を5年で12倍に成長(Keap社)
- 就任後に売上626%アップ(OtterBox社)
本書は、単なる理論ではなく、現実の成功につながった“実務書”でもあるのです。
「まえがき」から読み解く経営哲学
1. 成功の鍵は「学び続ける姿勢」
ガーバー氏は「成功者は、すでに知っていることではなく、常に学び続けようとする姿勢を持っていた」と語ります。
専門職出身の経営者は、職人としてのスキルを高めようとしますが、会社を成長させるには「ビジネスのつくり方」を学ぶ必要があります。
2. 社員と知識を共有する文化
経営者が持つ理念や財務情報、商品知識を社員と積極的に共有することが、組織全体の成長を促進します。
「会社は学校であるべきだ」とガーバー氏は述べています。
📌ポイント
- 経営理念
- 財務情報の開示
- 商品・サービスの理解
これらを社員と共有することで、組織の一体感が生まれます。
3. ダブルビジョンの重要性
「経営者は、ビジョンと現実の両方を見据える存在」
ガーバー氏は、成功する経営者には“ダブルビジョン”があると説きます。
すなわち、未来を描く起業家的な視点と、現実を整えるマネージャー的視点、そして現場で動く職人としての視点を併せ持つ必要があります。
🧠【図解:経営者に必要な3つの人格】
- 起業家:未来を構想する
- マネージャー:仕組みを整える
- 職人:品質を守る現場の達人
「はじめに」に込められたメッセージ
1. 「事業は経営者の鏡である」
会社のあり方は、経営者の考え方・働き方を反映しています。
経営者が杜撰なら会社も杜撰に、誠実であれば会社も誠実になります。
だからこそ「自分を変えること」が、経営改善の第一歩なのです。
2. 責任を“仕組み”に向ける
人に責任を求めるのではなく、仕組みに目を向ける文化が重要です。
仕組みの欠陥こそが問題の本質であり、それを改善するのが経営者の役割です。
ビジョンと仕組みはセットで機能する
本書が伝えるのは、「仕組みづくりはビジョン実現の手段である」ということ。
どんな仕組みも、最終的に「何のために存在するのか」が問われます。
創業期から壮大なビジョンを描くのは難しいかもしれません。
しかし、事業を進めていく中で、自身の成長とともにビジョンも明確になります。
💡「山頂に登ってはじめて、それが本当の山頂ではなかったことに気づく」
ー ガーバー氏の名言
経営とは終わりのない旅です。ゴールにたどり着いたと思っても、それは次の出発点に過ぎないのです。
最後に:仕組み経営の第一歩を踏み出そう
ガーバー氏は、経営とは自分自身の人間性と向き合う旅だと説きます。
成功には、知識、仕組み、ビジョン、そして自己変革が必要です。
次回以降、本書の各章をより詳しく解説していきます。
ぜひ今後もお付き合いください。