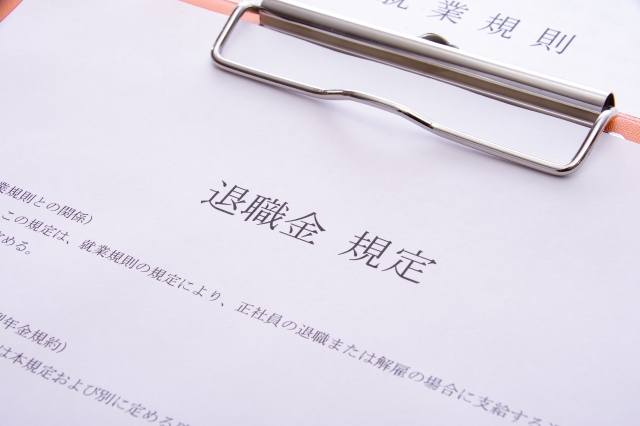
はじめに
人手不足と賃金上昇の時代。
中小建設業にとって、「給与だけで社員をつなぎ止める」時代は終わりつつあります。
今後の人材戦略では、「総報酬(トータルリワード)」の発想が鍵になります。
総報酬とは、給与・賞与だけでなく、手当・教育・評価・働きやすさなど、社員が会社から得られるすべての価値を指します。
本記事では、建設業における「総報酬経営」の実践策を解説します。
1. なぜ「給与アップ」だけでは定着しないのか
一時的な賃上げでモチベーションは上がっても、長続きしません。
建設現場の離職理由を調べると、実は次のような項目が多いのです。
| 主な離職理由 | 比率(建設業界調査) |
|---|---|
| 人間関係・職場環境 | 約35% |
| 仕事のやりがい・評価不満 | 約25% |
| 給与・待遇への不満 | 約20% |
| 将来の不安 | 約15% |
つまり、「給与水準」よりも「働く環境」「評価の納得感」「成長実感」が重視されています。
この構造を踏まえ、“総報酬”で社員を惹きつける戦略が必要です。
2. 総報酬を構成する4つの柱
【総報酬の構造】
1. 金銭的報酬(給与・賞与・手当)
2. 成長的報酬(教育・資格・スキル)
3. 感情的報酬(感謝・承認・信頼)
4. 生活的報酬(働きやすさ・福利厚生)
この4つをバランスよく設計することが、社員満足と経営安定の両立につながります。
3. ボーナス・手当制度を見直すポイント
(1)成果と連動するボーナス
ボーナスを“年功的支給”から“成果連動型”に切り替えることで、社員の行動が変わります。
| 指標例 | 内容 |
|---|---|
| 工事利益率 | 目標達成で加算 |
| 安全・品質 | 無事故・不具合ゼロで加算 |
| 改善提案 | 現場改善・原価削減の提案数で加算 |
→ 「頑張れば報われる」仕組みが現場の士気を高めます。
(2)生活を支える手当の整理
建設業では、現場手当・通勤手当・家族手当などが多岐にわたります。
複雑な制度は不公平感を生みやすいため、**「生活支援+成果評価」**の2軸で整理します。
💡 例:
・現場手当:現場責任者・管理職に明確な基準を設定
・資格手当:保有資格に応じて定額支給(施工管理技士など)
・通勤・住宅手当:実費支給を基本とし、透明性を高める
(3)小さな「感情的報酬」が効果大
月次で社長からの感謝メッセージや、社内表彰制度を導入するだけでも、社員のモチベーションは大きく変わります。
💬 実例:
「安全表彰」「現場貢献賞」「お客様満足賞」など、
手当は1万円でも、“見られている・認められている”感覚が定着率を高めます。
4. 総報酬を「見える化」する
社員にとって、自分がどれだけの価値を会社から受けているのかは見えづらいもの。
そこで、「総報酬通知書」(年1回)を発行する企業が増えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本給・賞与 | 金銭的報酬 |
| 各種手当 | 現場・資格・通勤等 |
| 教育・研修 | 年間受講費・資格支援額 |
| 福利厚生 | 制服・安全装備・社用車利用 |
| 合計価値 | 年間○○万円相当 |
→ 「自分はこの会社からこれだけの価値を受けている」と実感できる仕組みです。
図解:総報酬経営のイメージ
給与アップ(短期満足)
↓
総報酬設計(長期満足)
↓
社員定着・生産性向上
↓
利益率アップ・再投資
5. 補助金を活用して制度導入を後押し
報酬制度や教育制度の整備にも支援制度が利用できます。
| 制度名 | 対応内容 |
|---|---|
| 人材開発支援助成金 | 教育・資格取得・評価制度設計を補助 |
| 業務改善助成金 | 賃上げ+制度改善で最大600万円助成 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 福利厚生や労務環境改善を支援 |
これらを組み合わせれば、制度づくりの初期費用を大幅に軽減できます。
チェックリスト:総報酬制度の整備状況(6項目)
- 賃金・手当・賞与の基準を明文化しているか?
- 成果連動ボーナスの仕組みを導入しているか?
- 社員教育・資格支援の制度を設けているか?
- 感謝・表彰など非金銭的報酬を実践しているか?
- 総報酬通知書を発行しているか?
- 助成金を活用して制度構築を行っているか?
まとめ
給与だけで人は動かず、手当だけでも人は定着しません。
**「お金+学び+感謝+安心」**の4要素が揃って初めて、人は会社に誇りを持ちます。
中小建設業が今後生き残るには、
“人を惹きつける給与体系”ではなく、“人が育つ報酬体系”への転換が不可欠です。


