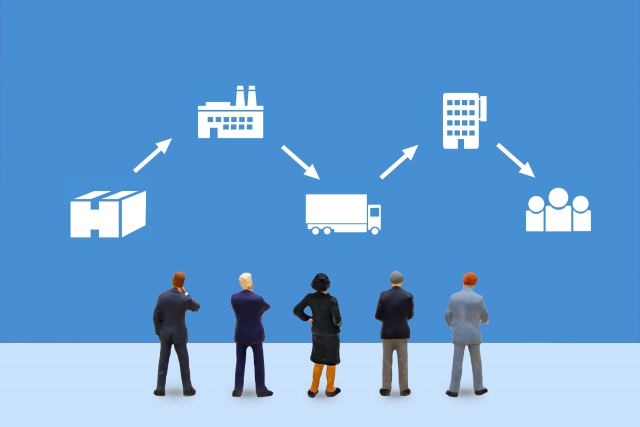
はじめに
「いつもの仕入れ先に注文したら、“在庫がない”と断られた」――
資材不足や納期遅延が当たり前になった昨今、こうした事態は珍しくありません。
中小建設業にとって、調達先が1社に偏ることは大きな経営リスクです。
本記事では、資材高騰や供給不安定の時代における「調達先分散化(マルチソース)」の考え方と、実際の実践ステップを解説します。
1. なぜ調達先の分散が必要なのか
建設業では、「長年の付き合い」「信用できる取引先」という理由で仕入れ先を固定している企業が多くあります。
しかし、次のような環境変化により、単一取引への依存はリスクになりつつあります。
| リスク要因 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 資材価格の変動 | 特定商社の価格上昇に依存 |
| 物流トラブル | 運搬遅延・欠品による工期遅延 |
| 災害・事故 | 工場停止・供給停止による操業ストップ |
| 取引条件変更 | 支払い条件や数量制限の強化 |
つまり、「安定した取引先が1社ある」という安心感が、逆に事業継続のリスクになるのです。
2. 調達リスクが利益を削る構造
仕入れ先1社依存
↓
価格上昇・供給不安
↓
材料不足・納期遅延
↓
工期延長・外注増
↓
利益率低下・信用低下
工事が止まれば、労務費や外注費が増え、利益を圧迫します。
さらに納期遅延によって顧客の信頼を失えば、次の受注にも影響します。
3. 調達先分散化の実践ステップ
Step1:現状の調達構造を“見える化”
まずは、主要資材ごとの調達依存度を把握します。
| 資材名 | 主仕入れ先 | 割合 | 代替先 | 在庫状況 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | A商社 | 80% | B商社 | 有 |
| 配管部材 | B問屋 | 100% | なし | 少 |
| 塗料 | C販売店 | 60% | D販売店 | 有 |
このように一覧化することで、「代替ルートがない資材」を特定できます。
Step2:第2・第3の取引先を確保
主要資材について、最低2社以上の取引ルートを確保しましょう。
地域の商社・専門問屋・ネット仕入れサイトなど、複数チャネルを比較することが重要です。
💡 実践ポイント
・見積を複数社から取得して単価を比較
・取引量を分散し、関係を維持
・万一の際には「緊急供給ルート」を確保
特に災害や突発的な供給停止時には、既存の関係性があるかどうかで対応スピードが大きく変わります。
Step3:BCP(事業継続計画)として仕組み化
調達リスク対策は、**BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)**の一部として文書化しましょう。
📄 内容例
- 代替仕入れ先一覧
- 緊急時の連絡フロー
- 主要資材の安全在庫基準
- 契約先の災害・事故対応体制
中小企業庁や自治体でも「BCP策定支援」があり、専門家派遣や助成制度を活用できます。
4. 調達分散とコストのバランス
「分散化=コスト増」という誤解がありますが、実際には価格交渉力の向上や取引条件改善につながるケースも多いです。
📊 事例:
仕入れ先を2社体制に変更 → 競争原理が働き、主要資材単価が平均5%下落。
また、複数社に発注を振り分けることで、納期の安定化・欠品リスクの低減にもつながります。
図解:調達分散の効果イメージ
【従来】A商社100%依存
→ 価格上昇・納期遅延に弱い
【改善後】A商社70%+B商社30%
→ 価格交渉力UP・供給安定・リスク分散
5. デジタル活用でリスク低減
調達データをスプレッドシートやクラウドで管理すれば、
どの商社・問屋から何をどれだけ買っているかを即座に把握できます。
💡 推奨ツール例:
・Googleスプレッドシート(在庫・仕入管理)
・クラウド会計ソフト(仕入先別支出分析)
・IT導入補助金での発注管理システム導入
これにより、属人的な「担当者任せ」から脱却し、組織的な調達管理が可能になります。
チェックリスト:調達リスク管理の5項目
- 主要資材ごとの仕入れ先依存度を把握しているか?
- 代替仕入れ先を2社以上確保しているか?
- 緊急時の調達ルートや連絡体制を整備しているか?
- 価格交渉や契約条件の見直しを定期的に行っているか?
- 調達データをデジタルで管理しているか?
まとめ
調達先の分散化は、単なる「仕入れ管理」ではなく、経営リスクの回避策です。
1社依存を脱し、複数のパートナーと信頼関係を築くことで、価格・納期・供給すべての安定化が図れます。
“万が一”に備えることが、“毎日の安定”を支える――それがこれからの建設経営に求められる視点です。


