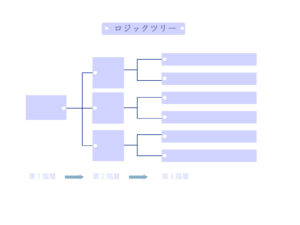日々の業務の中で「問題の本質が見えない」「原因が複雑すぎて整理できない」と感じることはありませんか?
そんな場面で役立つのが、問題の構造を図解で明らかにする「連関図法(Relation Diagram)」です。
特に人事、営業、企画といった多くの言語情報を扱う部門で効果を発揮し、チームでの「なぜなぜ分析」を視覚的にサポート。
本記事では、連関図法の基本から活用方法、テンプレートの使い方や実際の事例までをわかりやすくご紹介します。
連関図法とは?
問題と原因のつながりを“構造化”する手法
連関図法は「新QC七つ道具」の一つであり、複数の原因とその関係性を可視化することで、課題の根本原因(真因)を特定するためのツールです。
連関図のイメージ図:
┌────────────┐
│ 問題(テーマ) │
└────────────┘
↑
┌─────┬─────┐
↓ ↓ ↓
一次原因A 一次原因B 一次原因C
↑ ↑ ↑
二次原因A1 二次原因B1 二次原因C1
連関図法が活きる3つのシーン
- 複雑な問題の原因が多すぎて混乱している
- 会議で課題を共有し、納得感ある議論をしたい
- “なぜなぜ分析”が深まらず、対策が曖昧になっている
たとえば、「顧客対応が遅い」「売上が伸びない」「社内コミュニケーションが不足している」といったテーマに対して、多角的な要因が関与している場合、連関図法が有効です。
連関図法の進め方:5つのステップで実践
STEP1:テーマの明確化
分析の起点となる「問題」を簡潔に記述します。
例:「顧客対応が遅延している」「生産性が低下している」
STEP2:原因の洗い出し
関係者でブレインストーミングを行い、思いつく原因をすべて出します。
- 体言止めは避ける(例:「情報共有の不足」ではなく「情報共有ができていない」)
- 1枚1要因を意識し、付箋やツールを活用するのが効果的です。
STEP3:図の中央にテーマを配置
模造紙やホワイトボード、オンラインツール(例:Miro, Jamboardなど)にテーマを中央に配置し、そこから放射状に図を展開します。
STEP4:因果関係を整理
矢印を用いて「原因→結果」の流れをつなげ、1次→2次→3次と深掘りします。
STEP5:主要因を特定
全体を俯瞰して、テーマに強く影響している要素(=真因)を選びます。太枠や色を変えて、見やすく強調すると良いでしょう。
活用テンプレートの例:顧客対応遅延のケース
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 顧客対応が遅れている |
| 一次原因 | 担当者の業務量が多い、連携ミスがある |
| 二次原因 | 情報共有不足、属人化した業務 |
| 三次原因 | マニュアル未整備、教育が不十分 |
| 主要因 | マニュアル整備と教育体制の欠如 |
このように「構造」と「関係性」を図解することで、チーム内の共通理解が深まり、解決への道筋が明確になります。
活用事例:3S活動の停滞を打破した成功例
テーマ:3S(整理・整頓・清掃)活動が進まない
連関図法による分析では、次のような原因が浮かび上がりました。
- リーダー教育が不十分
- メンバー教育が行き届いていない
- 会議の目的が不明確で時間管理が甘い
これらを主要因として特定し、以下の改善策を実行:
- 教育プログラムの再構築
- 進捗確認会議の設計見直し
結果、活動の定着率が大きく向上し、部門全体の業務改善が進展しました。
活用ツール:デジタルでも簡単に作成可能
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Miro | オンライン共同編集が可能なホワイトボード型 |
| Google Jamboard | Googleアカウントで無料使用可能 |
| Canva | 図解テンプレートが豊富でビジュアルに強い |
| Lucidchart | 高機能で複雑な図解も柔軟に作成可能 |
※付箋+模造紙も、アナログながら有効です。
まとめ:連関図法で“チームの課題解決力”を高めよう
連関図法は、複雑な問題の原因と構造を「見える化」することで、以下の効果をもたらします。
- 問題の本質をつかみやすくなる
- チームでの建設的な議論がしやすくなる
- 対策が具体的かつ実行可能になる
多くの業種・職種において活用できる汎用性の高い手法です。
定例会議やプロジェクト振り返りの中で、ぜひ取り入れてみてください。