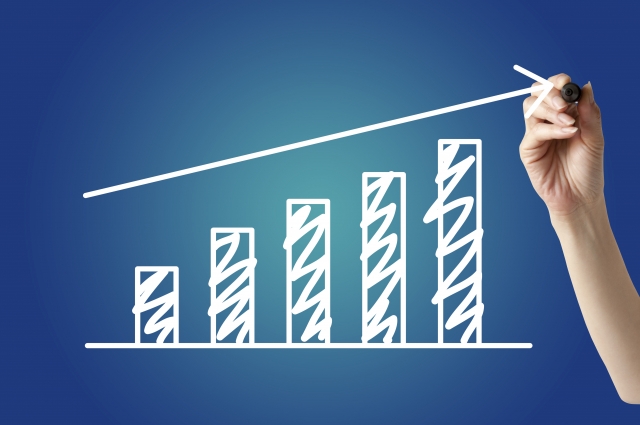
企業の成長性を評価するうえで、売上の増減だけでなく、利益の推移を把握することが欠かせません。特に「経常利益増加率」は、企業の本業を含む日常的な事業活動から得られる利益の成長度合いを示す重要な指標です。
本記事では、経常利益増加率の基本から、実務での分析ポイントまでを解説します。
経常利益増加率とは?
経常利益増加率とは、前期と比べた当期の経常利益の増減をパーセンテージで示す指標です。企業の利益体質や収益性の改善度合いを測るうえで、非常に有効です。
計算式は以下の通りです:
経常利益増加率(%)=(当期経常利益 − 前期経常利益)÷ 前期経常利益 × 100
経常利益は、本業から得られる営業利益に加え、営業外収益(例:受取利息や配当金など)を加え、営業外費用(例:支払利息など)を差し引いた利益です。
つまり、企業の日常的な経営活動の結果を反映しており、この利益が伸びているということは、企業の実力がついてきていると判断できます。
図解:売上・利益の増減と企業の状態の分類
以下のように、売上と経常利益の増減によって、企業の状態は大きく4つに分類されます。
+------------------+--------------------------+
| 売上 / 利益 | 増加 | 減少 |
+------------------+--------------------------+
| 増加 | ①増収増益 ③増収減益 |
+------------------+--------------------------+
| 減少 | ②減収増益 ④減収減益 |
+------------------+--------------------------+
それぞれの状態に応じた分析と対応策が求められます。
状況別:経常利益増加率の見方と改善のヒント
① 増収増益(理想的な成長)
売上と利益がともに増えている場合、基本的にはポジティブに捉えられます。ただし、その成長が持続的かどうか、売上の中身(採算性の高い商品かどうか)もあわせて確認しておきましょう。
② 減収増益(選択と集中の成功)
売上が減っているにもかかわらず、利益が増えているケースです。たとえば、採算の悪い事業や商品を整理し、利益率の高い分野に集中した結果、利益が改善することがあります。
一方、偶発的な要因(人件費の減少、特別な費用の削減など)であれば、一時的なものと認識し、長期的な成長戦略の再検討が必要です。
③ 増収減益(コスト増加の兆候)
売上は増加しているのに、経常利益が減っている場合は注意が必要です。まずは「売上総利益」の動向を確認しましょう。売上総利益が減っているなら、商品の採算性が低下している可能性があります。
この場合、以下のような視点から採算分析を行いましょう。
- 商品別・地域別・チャネル別の利益構造
- 原価高騰の影響有無
- 競合との価格競争状況
さらに、差別化戦略や販売戦略の見直しも必要です。たとえば、以下のような施策が考えられます。
- 高採算商品への集中販売
- 品質・機能・アフターサービスによる競合との差別化
- 利益率向上を意識したプロモーション戦略
一方、売上総利益が増えているにもかかわらず、経常利益が減っている場合は、「販管費」や「支払利息」などの経費が増加していると考えられます。経費構造を見直し、業務の効率化やコスト削減に取り組む必要があります。
④ 減収減益(危機的状況の可能性)
売上も利益もともに減少している状況です。まずは売上の減少要因を明確にし、以下の視点で対策を検討します。
- 商品の競争力・需要動向の変化
- 顧客ニーズとのズレ
- マーケットシェアの喪失
加えて、原価管理や販管費の削減を進め、経費全体の見直しを行うことが求められます。根本的なビジネスモデルの見直しが必要な場合もあるでしょう。
利益重視の経営が安定成長の鍵
売上は企業活動の基盤ですが、安定した経営を実現するためには、最終的に「利益」を確保できるかどうかが重要です。売上の増減だけで一喜一憂するのではなく、利益指標と併せて、全体のバランスを見ながら経営判断を下すことが求められます。
まとめ
経常利益増加率は、企業の実力や成長性を測る重要な指標です。しかし、単年度の増減にとらわれるのではなく、売上や費用の構造とあわせて、より立体的に分析する視点が必要です。
経常利益が増えていれば安心というわけではありません。増益の理由が何なのか、減益であればどこに課題があるのかを掘り下げて分析することが、次なる経営判断に役立ちます。
図解や定量的なデータとともに、利益構造を見直し、自社のポジションと課題を的確に把握しましょう。


