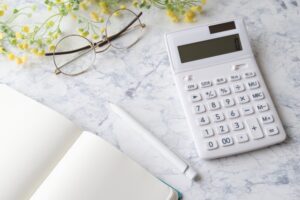省力化補助金では、優れた計画書を作っているつもりでも
「実は不採択になりやすい要素」を無自覚に入れてしまっている企業が非常に多いです。
第1回・第2回の採択結果を分析すると、
不採択案件には“共通する落とし穴” が存在します。
本記事では、支援現場で最も多い
不採択ポイントTOP5 をわかりやすくまとめました。
【1】課題が抽象的で、設備とつながっていない(最も多い原因)
不採択案件の8割近くに見られたのがこれ。
▼典型的なNGパターン
- 「人手不足が課題です」
- 「作業が属人化しています」
- 「この設備で効率化できると思います」
→ すべて抽象的で、数値がない。
▼審査官が求めるのは「問題の定量化」
- Before何分 → After何分
- 月間工数何時間 → 何時間へ
- 不良率何% → 何%へ
“課題 → 設備 → 効果” がつながらないと評価はつきません。
【2】設備が省力化に直結していない(対象外判定)
第1回・第2回の不採択案件で特に多かったのが、
「そもそも対象外の設備」を申請しているケース。
▼不採択になりやすい設備
- ホームページ
- ECサイト
- パソコン単体
- 防犯カメラ
- 営業管理ソフト
- デザイン制作物
- SNS運用ツール
これらは省力化(=現場の人手削減)と直接紐づかないため、
審査官は評価を付けようがありません。
【3】効果計算が机上の空論(数値の根拠なし)
採択結果の審査コメントで最も目立った指摘は、
「効果の根拠が弱い」
「増産効果が現実的でない」
というもの。
▼ダメな例
- 「年間1,000時間削減できる見込み」
→ どうやって?計算式は?根拠は?の説明がない。
▼採択されやすい例
- 作業45分 → 自動化で5分
- 月200回 → 年間800時間削減
- 1時間あたり労務費2,000円 → 年160万円の効果
計算式が明確なものは審査官も評価しやすいです。
【4】賃上げ要件の理解不足(要綱違反で減点)
省力化補助金は 賃上げが制度の根幹 です。
よくある不採択理由は、賃上げ要件の誤解です。
▼要綱の正式要件
賃上げ要件は 「①または②」+③ の両方が必要。
① 給与支給総額の年平均成長率 +2.0%以上
② 1人当たり給与支給総額の年平均成長率が
都道府県最低賃金の直近5年平均成長率以上
③ 事業場内最低賃金が最低賃金 +30円以上
▼NGパターン
- “2%だけ増えていればOK”と思っている
- 最低賃金+30円が必要と知らない
- 「賃上げはする予定です」と抽象的に書いている
賃上げ計画が曖昧な申請は確実に減点されます。
【5】運用体制が曖昧(導入後の運用が見えない)
第1回・第2回不採択案件に多いのが、
「設備を買うところだけ書いている」申請です。
審査官は
“設備を使いこなせるか?”
を非常に重視します。
▼NG例
- “現場全体で運用します”
- “従業員が対応します”
→ 何も伝わらない。
▼採択されやすい書き方
- 操作教育:2週間、担当者Aが実施
- 故障対応:メーカーBが年間保守
- 効果測定:月1回、工程別の工数を確認
- 現場責任者:C氏(経験15年)が指揮
運用体制が具体的なほど評価が高くなります。
【まとめ】
不採択の傾向と落とし穴5選(第1回・第2回分析)
不採択を招く共通ポイント
- 課題が抽象的で、設備と効果がつながっていない
- そもそも省力化と関連しない設備を申請している
- 効果計算が曖昧で、根拠が説明できない
- 賃上げ要件を誤解しており、要綱とズレている
- 運用体制が不十分で、導入後の運用が見えない
これらを避けるだけで、
計画書の完成度と採択率は大きく改善します。