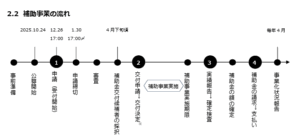― 国が支援する「再建の設計図」
■ はじめに:経営改善計画は“再建の設計図”
「資金繰りが苦しい」「借入金の返済が重い」「取引銀行との関係をどう立て直せばいいかわからない」――
そんな経営課題を抱える中小企業にとって、経営改善計画は「再建の設計図」となる存在です。
経営改善計画とは、企業が自社の現状を分析し、今後の経営方針・改善策・資金計画を体系的にまとめた再生のための計画書です。
単なる書類ではなく、**「金融機関が納得し、経営者自身が実行できる現実的なプラン」**であることが重要です。
■ 国が制度化した「経営改善計画策定支援事業」とは
経営改善計画の作成は、専門的な知識が必要であり、経営者一人でまとめるのは難しい場合が多くあります。
そのため、国は2013年以降、中小企業経営力強化支援法に基づき、「経営改善計画策定支援事業」を制度化しました。
この制度は、**国が認定した専門家(=認定経営革新等支援機関)が企業をサポートし、計画策定にかかる費用の一部を国(中小企業活性化協議会)**が補助する仕組みです。
💬 簡単に言えば、
“国公認の専門家と一緒に再建計画を作り、その費用を国が支援してくれる”
という中小企業向けの公的支援制度です。
■ 2つの支援制度:早期経営改善計画と405事業
経営改善計画策定支援事業には、企業の状況に応じて2つのタイプがあります。
| 制度名 | 対象 | 補助上限 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 早期経営改善計画(バリューアップ支援) | 資金繰り管理・採算改善を早期に行いたい企業 | 上限25万円(3分の2補助) | 軽度な経営課題向け。金融機関への提出を通じて自助改善を促す。 |
| 経営改善計画(405事業) | 借入返済や金融支援が必要な企業 | 上限300万円(3分の2補助) | 本格的な再建支援。DD(調査)+計画策定+伴走支援。 |
どちらの制度も、**認定支援機関(税理士・診断士・商工会など)**が企業を支援します。
状況に応じて「早期」→「405」へステップアップすることも可能です。
■ なぜ今、経営改善計画が重要なのか?
物価高・人件費上昇・円安による原価高騰――
中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
一方で、金融機関の姿勢も変化しています。
従来の「貸す・返す」関係から、**「事業性評価に基づく共創関係」**へ。
その評価の基礎となるのが、経営改善計画なのです。
つまり、経営改善計画は
- 金融機関と同じ目線で数字を共有する
- 自社の課題を客観的に分析する
- 改善行動を継続的に実行する
ための“共通言語”となります。
■ 経営改善計画の内容
計画書の中身は、おおむね以下の構成です。
- 現状分析(財務・組織・市場環境)
- 課題の整理と優先順位づけ
- 改善策の具体化(売上・原価・人件費・資金繰り)
- 実行スケジュール・モニタリング方法
- 資金繰り表・損益計画・返済計画
この計画を基に、金融機関と再建方針を共有し、条件変更や追加融資、保証解除などにつなげていきます。
■ 認定支援機関と取り組むメリット
- 国の補助で費用負担が軽減(上限25万円または300万円の3分の2)
- 専門家のサポートで「金融機関が納得する計画書」が作成できる
- 伴走支援で「計画の実行」までサポートを受けられる
経営者にとって最大の価値は、**“自社の数字と真剣に向き合える時間”**を持てることです。
経営改善計画は、数字を「管理する」だけでなく、「経営の本質を見直す」きっかけになります。
■ まとめ:経営改善計画は「再挑戦のスタートライン」
経営改善計画は、“再建”だけでなく“再挑戦”の始まりです。
金融機関との信頼関係を再構築し、次の成長ステージへの足がかりを作るための公的支援制度。
もし今、
「資金繰りに余裕がない」「業績悪化で融資が通らない」
と感じているなら、まさに経営改善計画の出番です。