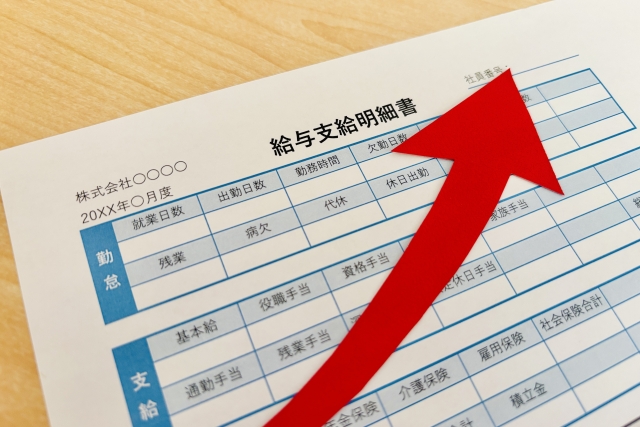
はじめに
最低賃金の上昇は、建設業における最大の経営圧力の一つです。
2025年度の全国平均最低賃金は約1,100円に達し、政府は「1,500円時代」を見据えています。
一見、社会全体にとって良い流れのように見えますが、中小建設業にとっては人件費負担の急増を意味します。
本記事では、最低賃金上昇がどのように経営を圧迫しているのか、そして「賃上げに耐えられる体質」へと変えるための考え方を整理します。
1. 最低賃金の推移と今後の方向性
ここ10年間で最低賃金は全国平均で約30%上昇しています。
| 年度 | 全国平均(円) | 上昇率 |
|---|---|---|
| 2015年 | 798円 | – |
| 2020年 | 902円 | +13% |
| 2023年 | 1,004円 | +11% |
| 2025年(見通し) | 約1,100円 | +10% |
特に都市圏ではすでに1,200円台に達しており、建設現場の日給・月給にも連動しています。
さらに「人手不足手当」「交通費」「安全手当」などを含めると、実質的な人件費は過去最高水準です。
2. なぜ建設業は影響が大きいのか
建設業のコスト構造のうち、労務費は全体原価の約4割を占めます。
そのため、最低賃金の上昇率が5%でも、工事全体の原価は約2%上昇する計算になります。
さらに、建設現場では「最低賃金+α」が常識。
技能を持つ職人にはより高い賃金が求められるため、全体の賃金水準が押し上げられる波及効果があります。
3. 利益圧迫の構造を理解する
【売上高】100%
│
├─ 材料費 35%
├─ 労務費 40% → +5%上昇 → 42%
├─ 経費 20%
└─ 利益 5% → 3%に減少!
このように、人件費がわずかに上昇しただけでも、利益率が半減することは珍しくありません。
特に「下請け構造」「単価固定契約」の企業では、コスト上昇を販売価格に反映できないため、赤字リスクが高まります。
4. 経営者が取るべき対応策
(1)「生産性=売上÷人数」で見直す
単純な人件費削減ではなく、**一人当たり売上高(労働生産性)**を指標にすることが重要です。
生産性向上のためには、
- 現場のムダ作業を減らす
- 重複管理をなくす
- IT・クラウドによる現場連携を強化する
といった改善が有効です。
📊 例:
一人あたり売上 2,000万円 → 2,200万円へ改善できれば、
人件費10%アップでも利益率を維持できます。
(2)単価見直しと値上げ交渉
賃金上昇分を吸収するには、請負単価の見直しが不可欠です。
「人件費上昇により品質確保が難しい」とデータをもとに説明することで、取引先も納得しやすくなります。
💬 ポイント:
・現場の実労働時間・工程表を根拠に提示
・「安全・品質維持」のための賃金改定として説明
・複数社との価格比較ではなく「継続取引による信頼性」で交渉
(3)成果と連動する賃金制度を設計する
単に「一律で上げる」よりも、
- 工事の採算に貢献した社員
- 現場改善に取り組んだ社員
- 若手の指導・安全管理に貢献した社員
に対して報酬を上げることで、モチベーションを維持できます。
💡 「昇給=成果」への連動が明確な会社ほど、社員の定着率は高い傾向があります。
(4)補助金・助成金を活用する
賃上げに伴う生産性向上投資には、
- 業務改善助成金(厚労省)
- 省力化投資補助金
- 人材開発支援助成金
などが利用可能です。
「単なる人件費増」ではなく、設備投資や仕組み改革をセットで行うことが、長期的な利益体質への転換につながります。
チェックリスト:人件費上昇に耐えられる体質チェック(6項目)
- 一人当たり売上高を把握しているか?
- 労務費の月次推移をグラフで管理しているか?
- 単価見直しや価格交渉を定期的に行っているか?
- 成果連動型の昇給・賞与制度を設計しているか?
- 補助金・助成金の活用を検討しているか?
- 現場作業のムダ削減に取り組んでいるか?
まとめ
最低賃金の上昇は止められません。しかし、**賃上げを「経営危機」ではなく「企業成長のチャンス」**に変えることは可能です。
ポイントは、「人数削減」ではなく「一人当たりの付加価値向上」へと視点を転換すること。
そのための体制づくりを、今から始めることが求められています。


